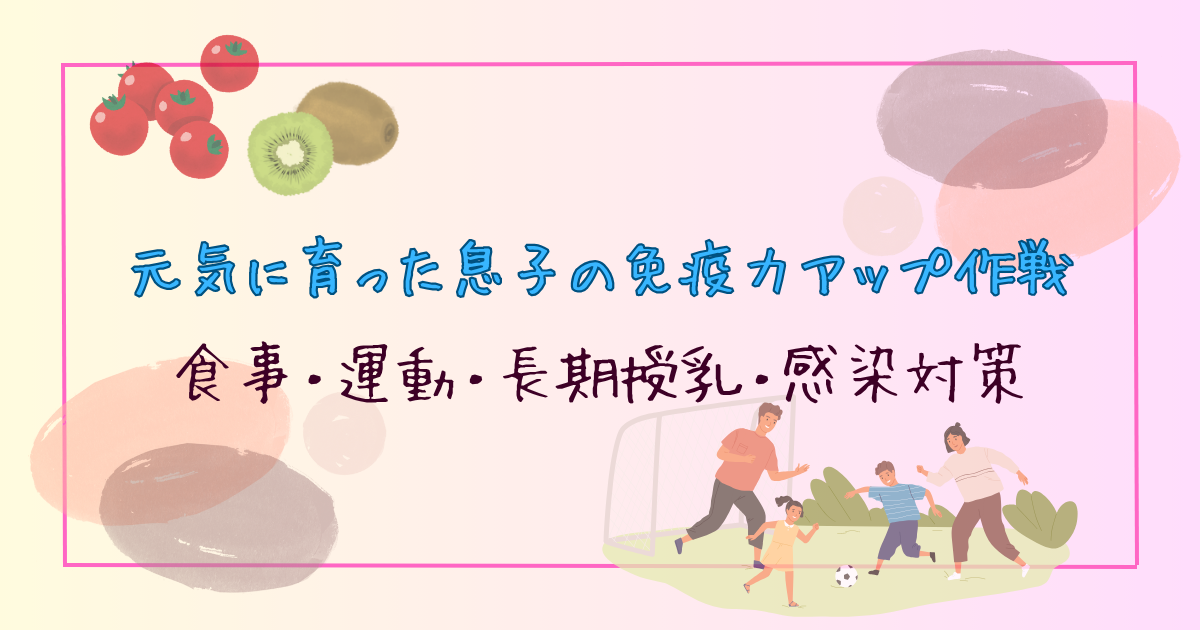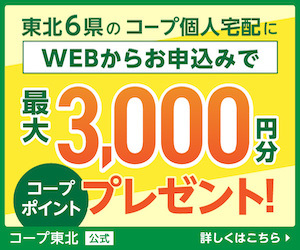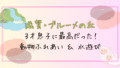こんにちは、ちびママです。
わが家の3才半を過ぎたちび小僧は、とにかく元気いっぱいです。
普段からほとんど風邪もひかず、タフな体に育ってくれています。
2才の冬に一度だけ、たぶん私からの感染でインフルエンザにかかりましたが、その時も比較的短い期間で回復していました。
(私やパパの方が長引き、ちび小僧の遊び相手をするのに苦労しました・・・)
もともと強い子だった?というのもあるかもしれませんが、これまでの食事・運動・長期授乳・日々の感染対策も大きく関係していると思います。
ただ元気すぎるがゆえに、私がいまだに手を焼いている悩み、『睡眠』についてもお話しします。
この記事では、元気いっぱいでほぼ病気知らずの息子を育てるために、わが家が実践したきた食事の工夫や、体をめいっぱい動かす遊び方をお伝えします。
お子さまの体づくりにお悩みのパパ・ママのヒントになればうれしいです。
生後半年間の『守りの育児』が作った元気の土台
遺伝的な健康運
ありがたいことに、ちび小僧は私たち親から特別な病気を引き継いだ心配はなく、生まれもった健康な体でスタートをきることができました。
乳児期によく起こる、突発性の熱や乳児湿疹など、いつ来るかと構えていましたがなかなか来ず。
初めて熱が出たのは1才を過ぎてからで、お腹をこわしたのは9か月の頃、12月に新潟へ帰省したときでした。
インフルエンザのときはさすがに熱がさがるまではぐったりしていましたが、普段の風邪のときは、子どもによくある『熱があっても元気』な状態でした。
肌は、関節の内側に汗をかくせいで肌荒れするくらいだったので、しっかり保湿をする対策をとる程度でした。
この元気な体をもって生まれてくれたことは、何よりの強みだと感じています。
この遺伝的な元気の土台の上に、生後約半年間の『守りの育児』をプラスしました。
最低限の外出で、感染症から遠ざける
1人っこ育児だからこそできることかもしれませんが、生後半年間は必需品の買い物や予防接種以外はほとんど外出しませんでした。
3月1日生まれで、幼いうちの夏の暑さを避け、外出を控えたということもあります。
出産前は自由に行っていた、デパートやおしゃれなカフェに行きたい気持ちもありました。
SNSで、親子でオシャレをして外出を楽しんでいるママを見ると、『私はこんなに引きこもっていていいのか?』と思うことも。
同時に、もし0才のちび小僧を連れてお出かけして、自分は楽しめるのかな?と疑問もあり、いつぐずるかわからないちび小僧との外出は、大げさですが私にとっては時限爆弾をかかえているような気持ちでした。
1人で行けるなら行きたいけど、一緒に過ごすなら家が1番いいや!と私の気持ちを納得させました。
わが家は近所にドラッグストアもスーパーもあり、ベビーカーにのせて歩いて行けます。
ちび小僧を電車やバスの人ごみにさらすこともありません。
この時期に最低限の外出にとどめ、感染症のリスクから遠ざけたことが、いつも体調が良いという好循環を生んだのかもしれません。
生後半年内に買い物以外で外出したのは、いずれも感染リスクの低い場所でした。
- 私の友達と、子連れで家で遊ぶ
- じぃじばぁばの家に泊まる
- 車でひまわり畑へ
- 生後半年頃から児童館と公園
長期授乳で第二免疫の獲得。断乳ではなく卒乳を目標に。
1才頃に断乳を試みるママが多いと聞きます。
昔は1才で断乳していないほうが少数派だったようですが、最近の子育てでは『赤ちゃんとママが好きなだけ』に変わってきているそうですね。
1才以降の第二免疫の獲得のためにも、1才過ぎまで授乳を続けたいと思っていました。
授乳も最初の頃は吸いつけなかったり、血豆ができたりで苦戦しましたが、3か月目頃から徐々に母乳のみでお腹を満たしてくれるようになりました。
飲みたがる回数が多い方だったので、嫌がることなく1年以上続けられ、無事に第二免疫を獲得しました。
リアルタイムのオーダーメイド免疫!
授乳期間は予想外に長引いており、3歳半を過ぎた現在、まだ飲んでいる状況です。
寝る前と起きたときに、毎回ではないですがときどき飲むと言います。
免疫の面で、環境に合わせたリアルタイムの免疫サポートが期待できているのはありがたいです。
しかし私が長期授乳を続けている理由はそれだけではありません。
ちび小僧にとっておっぱいを飲む時間は、何にも代えがたい安心感を得られる時間だと思います。
なので私は卒乳時期を急がず、ちび小僧が自然と飲まなくなる日まで、この『タフな体と心』を育む授乳を続ける予定です。
食べる量は少なくてもOK。食より遊び好きな息子に実践した、栄養効率アップ術。
おっぱいはよく飲むちび小僧だったので、食べることにも期待していたのですが、離乳食をはじめても食事にはあまり興味をもっていない様子でした。
なので、育児書に書かれている時期よりも約1か月遅らせてゆっくりスタートしましたが、なかなか食が進まない日々でした。
食事椅子に座ってもすぐに遊びが気になってしまうちび小僧。
私にとっては『どうやって短い時間で栄養を確保するか』という戦いでした。
元気ならオッケー!と割りきり、私が実践したのが次に紹介する栄養効率アップ術です。
短時間勝負。食から気がそれないための『好きなもの優先&形』作戦。
お皿に好きな食べ物を1品は入れて、まずは食事へ誘います。

CL3
2才前半の晩ご飯です。右上の仕切り皿を先に出して食卓に座ってもらう感じです。
写真映えを全く考えていない写真ですみません。。。
自分の記録用に撮影できるときだけサッと撮った写真です。統一感がなく見にくいかと思いますがご容赦ください。。。
フルーツやプチトマトが大好きなので必ず入れます。
くだものは毎食だと果糖が多いといわれますが、食べることを優先しました。
プチトマトは栄養価が高いし、洗って出すだけで簡単なので、食べてくれて本当に助かっています。
離乳食の最初の頃は皮をむいてつぶしていました。
固形も食べられるようになると皮をむいて4等分に切り、その後様子を見て2等分にし、そして皮のまま食べるようになりました。
丸のままは窒息の危険があるし、口の中ではじけて汚れてしまうこともあるので、今でも半分には切っています。
「丸のままがいい」とリクエストがあると切れ目を入れています。
1食で3粒ほど、朝食以外で食べているので、なかなかの摂取量です。
そして少し食べて飽きてきたかなというタイミングで、めずらしい形にした食事を出します。
めずらしいといってもいつもと違うお皿に盛りつけたり、切りかたを変えたり型抜きをしたり、いつもと違うがポイントです。
例えば私は、食パンをいろんな形でだしてみました。

OR

OR

CL3

CL3

CL3
- 最初は短いスティック状
- 長いスティック状
- スティック状をカップに立てる
- サイコロ型
- 三角に切る
- そのまま
- 三角のサンドイッチ
- 四角のサンドイッチ
- くるくるサンドイッチ
- 型抜きする
- ツミキの原理で積んで出す
そのままというのが意外と心をつかみました。
ヨーグルトも毎日出していましたが、やはり飽きてくるようでした。
銘柄や容器をかえてみたり、ジャムやはちみつを入れてみたり、大人用のスプーンを渡してみたり。
それでも手をつけない時はお行儀は悪いですが、ストローを渡して「吸えるかな?」と聞いてみると完食してくれたりしました。(ストローをマスターしてからです)
スプーン、フォーク、箸、時にはピックも用意し、手づかみも含め、好きな食べ方でどうぞスタイルもとりました。
幼いうちはとくに、栄養とお行儀よりも、食べることを優先にすすめました。
長時間になると飽きてくるし、代り映えしないと興味をもってくれない。
なので、短時間で飽きないうちに、好きなものを食べてる間にちょっと工夫したいつもと違うを用意する。
そんな作戦で乗り切っています。
『食べてほしいけどうまくすすまない・・・』
手を焼いてパパ・ママは大変かと思いますが、固定概念にとらわれず、ママもちょっと笑って楽しんでしまうような盛り付けをしたり、ミスマッチなカトラリーを使ったりしてみてください。
意外とお子さまにヒットして食べてくれるかもしれません😊
栄養効率アップ。食が細い子を支えたわが家の定番食品。
『時間をかけて一生懸命作った料理を食べてくれなくて辛い・・・』
よくあることですよね。
私は手早く料理をすることが得意ではなく、産後は時間がなく簡単な調理方法で作っています。
夫と2人の頃は、韓国料理やスペイン料理も好きで作っていたのですが、子ども中心の食生活に変わりました。
たまに凝った幼児食にチャレンジしましたが、食べてくれず。
短時間調理で、食材そのものをシンプルにだすことが多いです。
凝ったものは市販のベビーフードに頼っていました😊
わが家の食卓によく登場する定番食品はこちらです。
- プチトマトとフルーツ
- 冷凍ブルーベリー
- レーズン
- ブロッコリー
- チーズ(鉄分入り)
- ゆで卵
- ツナ缶
- ささみ缶
- 魚肉ソーセージ
- ハム
- ソーセージ
- ミートボール
- しらす
- サケ
- サバ
- 肉
- キノコ
- ちくわ
- カニカマ
- はんぺん
- 厚揚げ
- 牛乳と豆乳
- 乳酸菌飲料
- ヨーグルト
- シリアル
- のり
基本、そのまま、切るだけ、ゆでるだけ、焼くだけ、チンするだけです。
しらすは、青のりと豆乳と一緒に卵焼きに入れています。
魚と肉は焼くだけ、肉は味付けしますが魚はそのままです。
牛乳と豆乳はまぜて朝食で飲んでいます。
無調整豆乳はクセがあるので、最初は豆乳少なめでしたが、今は半々で飲めています。
『鉄分入り』や『カルシウム入り』の食品は積極的に取り入れています。(栄養士のお友達の情報を参考にしています)
味噌汁にキノコ類を入れます。
何か混ぜ込めそうなものをいつも考えて、粉類や乾物を料理に忍ばせています。
- すりごま
- 青のり
- 粉納豆
- 枯れ節
- かつお粉
- アミエビ
- きな粉
- お釜にカルシウム
枯節は鰹節よりも、DHAとEPAとうま味成分がアップします。
納豆は食べなかったので、粉納豆を味噌汁やカレーに忍ばせています。
ごはんを炊くときにカルシウム+鉄分の粉を入れて炊きます。
おやつが大好きで、1日に何回も&おかわりも要求されるので、ヘルシーで栄養のあるものを探しました。
- 干し芋
- 茎わかめ
- 小魚せんべい
- ドライフルーツ
- 野菜チップス
- 凍らせたくだもの
- 手作りアイスキャンディー
- 果汁100%チューぺット
- 鉄分入りジュース
- 鉄分入りグミ
手作りアイスキャンディーは、フルーツの缶詰とリンゴジュースを100均のアイスキャンディーメーカーに入れて凍らせるだけの簡単なものですが、おいしくできます。
2才頃、おやつを食べても食べても要求され、私はかなりストレスを感じていました。
上記のようなおやつを出しても「これはおやつじゃない、袋に入ってるのがいい」と、4連パックになっているスナック的なものを要求されたり。
「好きにすれば!」「ごはんは食べないのに」というような言わなくてもいいことをちび小僧に向かって言ってしまったり・・・
ヘルシー&栄養おやつ作戦はうまくいくときばかりではないですが、上記のものを受け入れてくれたらラッキーと思い、まずは出してみています。
いかに簡単な調理で、少ない量の中に栄養を多く入れるか。それが私のテーマになっています。
栄養のために食べてほしいが食べなかったもの
栄養価の高い食材を選んで食卓にだしていましたが、食べないものもありました。
- アボカド
- 納豆
- ブロッコリースプラウト
- かたまりの肉
アボカドとブロッコリースプラウトは、1口食べたけどそれ以降は食べないのであきらめました。
納豆は粉納豆に、かたまりの肉はミンチ肉に変えて、食べてくれています。
(幼稚園年少入園後、かたまり肉も食べるようになりました。給食でいろんなメニューを食べるようになり、家の食事でも新しいものにチャレンジしてくれます。)
食べる量は少なくても、この短時間作戦と高栄養価作戦でタフな体を作ってきました。
皆様のヒントになればうれしいです。
遊びは最高のトレーニング。遊びで作る一生モノの強い体。
食の面では食べてもらうことに苦労していますが、遊びは逆に大好きすぎて困るほどです。
遊びに出かけ、帰る時間になっても「まだ遊ぶ!」と言い帰ろうとしてくれません。
公園、児童館、室内キッズパーク、商業施設など、一時期は幼稚園の帰り道もでした。
帰ってもらうために、家に目新しい遊びやおやつを用意して、なんとか帰っていました。
外遊び、室内遊びそれぞれで、元気の秘訣となる遊びをご紹介します。
外遊び
真夏と雨の日以外は公園が定番の遊び場です。
体力アップはもちろん、自然からたくさんの刺激を受けることも大切だと思い、外遊びはできるときにできる限りしています。
大人もリフレッシュでき、お子さまと集中して遊べる充実した時間になりますよね。
暑さ、寒さ対策をして自然の中でたくさん体を動かしましょう。
公園の遊具

CL3

CL3
公園の遊具は見つけると、駆け出さずにはいられないほど大好きです。
網が張り巡らされ、アスレチックのようになっている遊具では永遠に動き続けます。
安全に設計されていてパパ・ママも安心して見守れますよね。
子どもができそうでできない設計だったり、次に来たときはできたりして、成長を感じられます。
3才は基本的な身体動作が大きく伸びる時期で、走る、跳ぶ、登るなどの動作はどんどん取り入れたいです。
好奇心も旺盛になる時期なので、様々な要素が組み合わさった複合遊具は、この時期の発達を促すのに最適です。
自然林での遊び

CL3
公園内の自然林で、デコボコと木の根がはっている場所や、自然の斜面を駆け回ることも大好きです。
舗装された場所とは違い、不安定な足元で、無意識に体の中心でバランスをとろうとします。
体幹や下半身の筋力がつき、けがの予防や、のちの運動能力の土台になります。
夏には、公園内の浅い川で川遊びもします。

CL3
ウォーターシューズをはき網やバケツを持って探検したり、水鉄砲をしたり、生き物を探したり。
水の中は陸上よりも大きな力が必要となるため、より体幹や足腰の力を使います。
そしてなにより、豊かな五感と知的好奇心を育ててくれます。
自然の川は、本物の刺激にあふれています。
水の感覚、音、光が反射する水面、数えきれないほどの刺激をもらえます。
五感をフル活用することで脳が活性化し、認知能力、非認知能力、心の安定と豊かな感性が育ちます。
夏以外も川辺で、拾った葉やどんぐりを浮かばせたり投げたりして遊びます。
ストライダー
1才半の頃に始めたストライダーも良かったです。

CL3
ペダルがないので、常に地面を足でけりながら体の軸を意識し、バランスをとらなければいけません。
体幹とバランス感覚の強化は、ストライダーで得られる最大の効果です。
最初はハンドルを握りまたがって歩くだけでしたが、2才頃にはサドルにお尻をつけて、地面をけり進めるようになりました。
そこからどんどんスピードアップし、もう私の小走りでは追いつけません。
「ストップー!」「ゆっくり行って!」と叫んでいます。(笑)
今後自転車の購入も考えていますが、多くのストライダー経験者がスムーズに自転車に移行しているとのことで、それも期待しています。
ストライダーは、子どもの持つ『進みたい、バランスをとりたい』という本能的な欲求を満たしてくれる最高のツールだと思っています。
子どもがただ遊んでいるように見えても、彼らは一生懸命に自分の体と向き合い、挑戦し、達成感を得ています。
この時期にめいっぱい外遊びをすることで得られた強い体幹と自信は、きっとこれから先の、さまざまなスポーツや日々の生活で『生きる力の土台』となってくれると信じています。
あわせて読みたい:めいっぱい体を動かし、自然の刺激をたくさんもらえた、滋賀県にあるブルーメの丘での思い出のブログはこちらです。よろしければこちらの記事も参考にしてください。
室内遊び
夏場や雨の日は室内でも体を動かせる遊びを考えました。
外よりも空間に限りがある分、ケガの予防にも注意が必要です。
家では移動させられるものは移動し、危険な家具の角などにはクッションを置いたりし保護します。
家で体を動かす遊び

わが家では家で使えるトランポリンと、ジャンプボール(取っ手のついたバランスボールのようなもの)を購入し遊んでいます。
楽しみながら運動能力と脳の発達の基礎を築くうえでとても有効です。
体幹、バランス感覚、筋力、瞬発力、心肺機能の強化や、空間認知能力の発達などが養われます。

プラレールの線路を購入する前は、トランポリンで電車遊びもよくしました。
家にある座椅子、クッション、枕、椅子などでコースを作り、落ちないように進むオリジナルアスレチックゲームもおすすめです。
間隔を広げたりして、自分で難易度を調節します。
コースを作ることで思考力や空間認知能力の発達につながるし、実際にコースを進むことでバランス感覚や体幹と筋力の発達も促されます。
自治体が運営する児童館

CL3

CL3
大型遊具や図書コーナー、創作室が無料で利用できることが多いのが魅力です。
家の近くにあれば、往復さえがんばれば雨や暑さを避けて遊ぶことができます。
幼い頃はめいっぱい体を動かして遊んでいましたが、3才以降は他の小さいお友達に気をつけて遊ぶように伝えていました。
子どもなりに注意するようになり、社会性と精神的な成長につながっていると思います。
赤ちゃんに優しくできたときやお片付けができたときに、パパ・ママ・先生からポジティブな声掛けをされることで、子どもの自尊心が育ちます。
異年齢のお子さんとの交流も、児童館の良いところですよね。
児童館でパワーをセーブして遊んでいる分、公園などでは思い切り体を動かす時間を設けて、発散できるといいですね。
ショッピングセンター内のプレイスペース

周りのお子さんに気をつけながらですが、走ったり飛び跳ねたりして遊べます。
無料で楽しめるし、近くにフードコーナーがある施設もあり、休憩もできて助かります。
このような施設も、多様な子どもたちが短時間で入れ替わり遊ぶ場なので、社会性の練習の場となります。
初めて会うお子さんと、パパ・ママが驚くほどあっという間に仲良くなったりしますよね。
まさにコミュニケーション能力が育っています。
お友達と譲り合うこと、順番に使うことなどの集団生活の基本的なルールを身につけてほしく、いつも見守っています。
科学館や博物館

CL1
宇宙、化学、自然などをテーマに、体験型の展示や実験、プラネタリウム等があります。
ちび小僧と科学館に行ったときはイベントでスライム作りができ、楽しかったようで、また行きたいと催促されます。
まだ『知識を学ぶ場所』というよりは、遊びや実体験を通して『知的好奇心の芽を育む場所』となっているように感じました。
『不思議だな』『どうして?』という気持ちをたくさん刺激し、探求心をくすぐる場になります。
数百円の入場料でお手頃価格な施設が多いのもありがたいので、ぜひ利用してみてください。
大型室内遊園地、キッズパークへ行く

CL3
1時間○○円や1日○○円で運営されているキッズパークへ行くと、外の環境に左右されずに思いっきり体を動かすことができます。
ボールプール、トランポリン、アスレチックなどがあります。
お弁当を持って行ったり外食して、1日を過ごすのも楽しいですよね。
ただお安くはない料金がかかるため頻繁には行けないので、たまにのお楽しみで利用しています。
天候や季節によっては外遊びができない日が続き、お子さんがめいっぱい体を動かせずに寝る時間に影響してしまうこともあるかもしれませんが、室内でも体を動かす遊びが意外とたくさんあります。
外でも室内でも、遊びはすべてお子さまの成長につながっています。
『遊びは最高のトレーニング!』という意識をもつだけで、日常の景色が変わるかもしれません。
私は夕方の公園で、もうお風呂とご飯の時間がさし迫っているのになかなか帰ってくれないちび小僧を見て、そう考えるようにしています。(余裕があるときだけ)
目の前のお子さまが楽しく遊んでいる時間を、自信をもって見守ってください。
いつも一生懸命にお子さまの成長を支えているパパ・ママ、ご自身をほめてあげましょうね!
わが家の感染対策ルーティン
食事と運動に加えて、感染対策も徹底しています。
とくに外出先や幼稚園からの帰宅後は、少々口うるさいくらいに言っています。
帰宅後すぐお風呂作戦で、玄関を開けたら廊下と洗面所以外の部屋には行きません。
服や体についた菌やウイルスを、家に持ちこまないことを最優先しています。
これまでちび小僧とバトルを繰り広げてきて、できあがったルーティンがこちらです。
↓
靴下を洗濯機に投げ入れる
↓
ハンドソープで手を洗う
↓
洗面所でYouTubeをみながらアイスを食べる
↓
風呂に入る
↓
おやつを食べる
お風呂には足洗いマットを導入したことで、スムーズに入ってくれる日が一時期増えました。
初めは、先におやつがいい、手も洗わないというところからスタートし、現在『洗面所でYouTubeをみながらアイスを食べる』に落ち着きました。

CL3
私的にはまだ改善の余地ありで、玄関で靴下を脱いでほしいし、アイスの前にお風呂に入ってほしいところです。
アイスとおやつ両方食べる、これも間食が多くなり、ご飯の進みが悪いことに影響していると思います。
これからもバトルになるのを覚悟で、より良いルーティンにしていけたらと思います。
元気すぎるがゆえ?整わない睡眠リズム
食事、遊び、感染対策で体力をつけたがゆえになのか、睡眠問題に悩まされています。
夜も元気でなかなか寝てくれません。
1日めいっぱい遊んだ日も22時、23時と時間はすぎていき、親の方がダウンです。
私は『ちび小僧が寝たらしよう』と家事を残したものならば、一緒に寝落ちして朝を迎えることになります。
なので寝かしつけより家事優先になるは、寝るのが遅いから朝起きられないはで悪循環におちいっています・・・
今も続けている授乳で寝てくれたり、絵本の読み聞かせで寝てくれることもありますが、眠くならないと布団に横になることができないので、対策を考え中です。
みなさま、アドバイスを頂けるとうれしいです。。。
まとめ
わが家のちび小僧が元気に育ったのは、生まれもったタフさに加えて食事、運動、感染対策でサポートしてきたことが大きく関わっていると思います。
今のところ幼稚園で感染症の発生があっても感染していないし、便秘もありません。
本当にありがたく、遊びに集中でき、良い循環ができています。
あとは睡眠を整えれば無敵です(笑)
皆様のお子様が元気に成長されることを心より願っています。
読んでいただきありがとうございました。
このブログの他の記事をご覧になりたい方は『ブログのトップページ』をご覧ください。